木曽谷の奥座敷、王滝村。霊峰・御嶽山をはじめ周囲を山々に囲まれたこの地では、伝統野菜の継承や「あるものを生かす」調理の工夫など、独自の食文化が豊かに育まれてきました。
「王滝村の郷土食を学びながら、新たな視点を取り入れた「新メニュー」を開発し、未来に伝えていけたらーー」。長野県立大学の健康発達学部 食健康学科のみなさんの、そんな想いからスタートしたのが、「郷土食キッチン」。「いっしょにやろうか」と集った、たくさんの村の人々に見守られて2025年2月、約1年をかけて取り組んだ「キッチン」の発表会と考案メニューの試食会が行われました。
ハードモードライフでは、発表に立ち会うとともに、学生のみなさんに、「王滝村、通ってみてどうでした?」と、交流を続けてきた感想を聞いてみました。
かぼちゃ団子、赤かぶ漬け、万年寿司・・・「王滝村は食文化の宝庫」
「王滝村に来ると、元気になれる気がするんです」
開口一番、そう話されたのは、長野県立大学健康発達学部食健康学科・中澤弥子教授。2024年秋から25年3月まで、学生たちとともに王滝村を訪れた印象を中澤先生は、「自然豊かで空気が澄み渡り、宝物のような食文化が残る土地」と語ります。
「食の体験では、瀬戸さん※のご協力で『ひだみ(どんぐり)』のおもちを食べられたのがとくに貴重で、ありがたい出来事でした。
また今回、新レシピ開発の対象となったかぼちゃ団子や大平、赤かぶ料理などについては、『これが正解のレシピ』というものがあるわけではなく、各個人、各家庭で味付けも調理法もさまざま。まさに、この『それぞれ違うおいしさがある』という魅力を大切に、バリエーションをまるごと残しておけたら良いのではないかと改めて思いました」(中澤教授)
※瀬戸美恵子さん。王滝村で長く食べられてきたどんぐり=「ひだみ料理」を現代に伝える料理店「庵 瀬戸」を営んでいる。

また、赤かぶについては、「ドレッシングに活用してみたところ、発色がとても美しくて。これはさまざまに活用ができるのではないかと、可能性を感じました」と、手応えを語ります。
なお、中澤教授が1月に王滝の小学生を訪れた際には、「思いがけず給食をご一緒させていただき、(すんきをチャーハンに入れた王滝のオリジナル給食)『すんたくチャーハン』を食べることができた」のだとか。この体験から派生し、「とくにうさぎの麹漬けなどは、伝統のつくり方をただ守るのではなく、口に入る場面でどのようにしたらおいしいのか、ここまでを体感し記録していくことが大切と感じた」と熱を込めます。
「王滝村の食は宝物。季節とともに移ろっていくその味を、千曲市のように『食ごよみ』で記録するのが良いのでは、と感じています。そして、文化庁が定める『全国各地の100年フード』への登録ができたら、とても素晴らしいですね。そのために、いま、みなさんの声を残しておくのがとても大切。私たちも引き続き、教えていただけたらと思います」
伝えるレシピ、広げるレシピ。アレンジメニュー発表&試食会開催

続いては、学生のみなさんによる発表の時間です。
「郷土料理キッチン」として全4回開催された集いで何が行われ、何を感じたのか、6名の学生たち一人ひとりがこの取り組みの概要と成果を伝えてくれました。
今回の取り組みでは、
- 冠婚葬祭で人が集まる時に作られる「大平(おおびら)」
- 土地の恵みを生かした「かぼちゃ団子」や「かぼちゃ汁粉」
- 赤かぶ料理
という3つの郷土料理をまず知ったうえで、大学生たちのアイデアをプラスし新たなメニューを考案していったのだとか。
さらに後半は、すんきチャーハン、王滝なます※1、こも豆腐※2、うずら・うさぎの麹漬けの4種を調理し、実食。加えて、村内で「庵 瀬戸」を営む瀬戸美恵子さんのご協力によりひだみ(どんぐり)を使った料理にも挑戦することができたと話します。
※1王滝なます・・・大根やにんじん、こんにゃくなどに、地域に生息する希少なきのこ「岩茸」などを加えてあえるなます
※2こも豆腐・・・豆腐をわらで包み、水分を抜くことで保存性を高めた郷土食
見たことも触れたこともない食材や料理の数々と向き合った数ヶ月間。学生のみなさんは「ひだみ料理が想像した以上にクセがなくおいしくて驚きました」「かぼちゃ団子は子どももいっしょの体験プログラムなどに向いているように感じました」「大平は、木手塩(きでしお)という大平専用の漆器でいただく体験も含めて心に残りました」など、心のこもった感想が次々に寄せられます。少し緊張しながらも、ていねいに想いを伝えるその様子に、会場に集まった村人たちも熱心に耳を傾ける、あたたかな時間となりました。

そして、発表がおわったあとは、学生のみなさんからの試食タイム!
中澤教授の研究対象でもある「おやき」と、王滝村での経験を組み合わせ、彼女たちが考案した、王滝村の食材を活かした新たなおやきがふるまわれました。
「できたてを届けたい」と、なんと前日に大学のある長野市でおやきをつくり、朝、あたためて王滝村まで運んできたとのこと。その情熱は会場にしっかりと伝わり、試食をしながら感想を伝え合う「交流タイム」は大いに盛り上がりました。


王滝の人たちは、家族みたいにつながっているー郷土食キッチンを終えて
緊張の発表と試食を終えて、約半年間にわたって行われてきた「郷土食キッチン」の取り組みもこれでひと段落。改めて、本プロジェクトに参加した6名の学生のみなさんに、感想をお聞きしてみました。
じつは、6名の学生のなかで、県内出身者はわずか2名。その他は栃木県や富山県、静岡県などから集っており、「自分の生まれ育った地域の食との違いに驚いた」との声が多く聞かれました。
「私の生まれ育った地域では、昆布やマス、魚のかまぼこなどが郷土食だけれど、こちらではウズラやウサギなどのジビエが郷土食で。自分の人生でジビエを食べると思っていなかったので、驚きました」とは、富山県出身の山﨑理央さん。飯田市出身の金田真希さんは「地元で思いつく郷土料理といえば、五平餅くらい。そもそも自分がこれまで、生まれた土地の郷土料理を意識したことがありませんでした」と話します。

そんななか、王滝村に通い、人々から聞き取りをした今回の経験のなかで驚いたことを語っていただくと、食文化と同じくらい王滝のコミュニティの深さに感動したという声が多数。
「村の方にレシピを習うと、必ずと言っていいほど『これは村の◯◯さんに教わったんだよ』という話が出てくるんです。私の地元で『ご近所付き合い』といえば、会って挨拶をしたり、たまに両親が清掃活動などに参加しているくらい。『家にあがって、いっしょに料理をつくる関係性の人がこんなにたくさんいるのってすごい』と、本当に驚きました」(金田さん)
そして、王滝村民の「人との距離の近さ・あたたかさ」は、来訪者である学生のみなさんにも向けられたのだとか。
「一度お会いしたら、最後には『次に会うとき、パンを焼いてきてあげるね』って声をかけてくださったり。『あれ、私ここに親戚がいたのかな?』って錯覚してしまうくらい、本当のおばあちゃんみたいに接してくれたのが、とてもうれしかったんです」(香取美友さん)
「私も、王滝村の人と人との関係の深さって、もはや以前留学したオーストラリアで出会った人みたいだなって感じてました。あるおばあちゃんから、『いつでもおいで、うちに泊まりなさい』って言ってもらえて。思い切り日本なのに、なんだか日本じゃないみたいな場所だよなあって、思っています」(七原さん)
また、なかには「万年寿司(まんねんずし)」や「すんき」など、個性的な郷土食にすっかり魅せられた学生も。こうしてすっかり村に打ち解けた学生たちの様子に、中澤教授も「どのように展開させることができるか、最初は手探りの部分もありましたが、ここまでかたちにできたのは、王滝のみなさんのおかげです。王滝村のみなさんが、こんなにも雄弁に郷土食を伝えられるのは、日頃から郷土食をつくり、そして人に教え合う文化が守られているからだと感じます」と話します。

数ヶ月の間に、たくさんの経験と出会いを得た学生のみなさん。最後に「王滝村を人におすすめするならどんな言葉?」と、キャッチコピーを即席で考えていただきました。彼女たちがここで過ごしたあたたかな時間がにじむその内容をご紹介し、今回のまとめとしたいと思います。
●長野県立大生が考える「王滝村って、どんな村?」
・村にあるもの、隅から隅まで食べ尽くせる村
・人とも自然とも、いっぱいつながる村
・心をつかんだら離さない村
・みんなが家族みたいな村
・一つ知れば、一気に深いつながりがもてる村
・心も体も、ぽっかぽかの村!

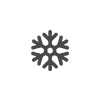 1°
1°