自然も暮らしもハードモード・・・なはずなのに、一度知ればまた通いたくなる、暮らしてみたくなる。そんな、王滝村の不思議な”吸引力”の秘密を探るべく、あえてふんわりとしたテーマだけ決めて、ゆるっと村歩き。ふいに出会った人々の声も交えながら、村の素顔をレポートするシリーズです。
王滝村ならではの「すんき」漬けの姿を探して
田畑や庭に初霜が降り、御嶽山が冠雪し、いよいよ本格的な寒さが訪れようとする、11月下旬。木曽の各地では、毎年冬に向けて欠かさず行われてきた、ある「しごと」が始まります。
それが、「すんき」漬け。
すんきとは、地域の在来品種である赤カブに茂った葉と茎を、塩を使わずに漬け込む、世界でも珍しい、無塩の漬物です。
塩を使わない、という珍しさに加え、近年、このすんきを発酵させている多数の乳酸菌がもたらす健康効果にも注目が集まっているため、耳にしたことがある人も多いかもしれません。

しかし、ひとくちに「すんき」と言っても、南北に広い木曽地方ではそれぞれに使うカブの品種や漬け方に微妙な違いがあること、ご存じでしょうか。
漬物専用の工房を構え、商品として広くこの文化を伝えるエリアもある一方で、王滝のすんきづくりはあくまでもアットホーム。
季節になると家の軒先に大きな樽を出し、家族や親族が食べるぶんをせっせと漬け込むーー、そんな習慣が毎年脈々と、受け継がれてきました。
と、いうわけで、
「王滝ですんきを漬けている人に話を聞きたい」
そして、
「冬に王滝を歩けば、誰かしらすんきを漬けているはず」
今回の「ふんわりテーマ」はこんな感じに設定。
早速、村の中心地である役場周辺を歩いてみることにしました。
捜索開始2分、「動かぬ証拠」を発見!?
まずはためしに、役場周辺をウロウロしてみる取材班。
すると、やっぱりありました、動かぬ証拠!
「森理容室・美容室」を営む森さん宅の前で、大きな樽と桶を見つけたのです。

この時季に、たっぷりと桶に水を溜めて、なにやら準備の予感。これは間違いなく、すんきを漬けているサインです。捜索開始からわずか2分ほどの出来事に一同、大興奮していると、ちょうど森さんご本人の姿が。
「もっ、森さん!!!」
駆け寄って声をかけてみると・・・

「あれ、どうしたのあんたたち?」
突撃取材にも関わらず、森さんは笑顔で出迎えてくださいました。
「じつは、家ですんきを漬けている人に、お話を聞きたいんです・・・」
遠慮がちに尋ねてみると、
「いいよ、もう漬かったすんきもあるから食べさせてやる。お茶しよ!」
と、あっさり快諾。
「あの部屋、使わせてもらえばいいさ、待ってて!」
と家の前の施設を指差したかと思ったら、再び家の奥へ戻っていき・・・
急展開で村営公民館の一室が、お茶飲み会場に決定しました(※)。
※管理事務所に許可をいただきました
気づけば、突然の「お茶飲み会」で、もてなされていた
・・・というわけで、突然のお声がけにも関わらず、茶飲み時間のスタート。
森さんお手製のすんき漬けと、王滝カブの甘酢漬けがテーブルに並びました。


まずは、鰹節をかけ、醤油をたらしたすんきから。
パリっと心地よい茎の歯ごたえ、そしてやさしい酸味がとってもおいしい!
続いて甘酢漬けも・・・

ん〜、コリっと食感よく、甘さと酸味のバランスが抜群。緑茶にもピッタリです!
そのおいしさに、質問したい気持ちがはやります。
森さん、おいしいすんきをつくるための「コツ」は、なんでしょう?
「それはまず、いい『モト』を使うこと。入れるタネがおいしくないと、おいしく漬からないの。
それから、いい菜っぱを使うこと。今年はなかなか、霜があたらんじゃん? そうすると、やっぱりよくないの。
あと、季節の最初に漬けたものより、漬け直しながら4度目、5度目くらいになったものがおいしい。木曽福島では毎年コンクールがあるんだけど、そのアンケートを見てもやっぱり、4度目、5度目がおいしいみたい」
なんと森さん、木曽町の恒例イベント「すんきコンクール」にも顔を出すほどの力の入れようだったとは。お見それしました。
「だって、みんなの(すんき)を食べてみることも大切。酸度も測ってみたりね。私のは、酸度は低いかもしれない、でも、私のは汁まで飲んでもおいしいの。みんな結局、自分の漬けるすんきが好きなのよ」
そんな言葉からも、深い「すんき愛」が伝わってきます。
「12歳になるころには、米俵一俵を背負っていたよ」
さて、続いてお茶飲みの輪に、佐口幸子さんが加わってくださいました。
じつは、佐口さんにはすんき漬けを見せていただけないかと事前にご相談していたのですが、「少し前にちょうど、漬けてしまったんだ」ということで、今回の取材は諦めていたのでした。
しかし、「せっかく取材にきたのなら」と、ご好意でお茶飲みの輪に参加いただけることに。森さんのすんきをいただきながら、昔話に花が咲きます。

「ここは本当に、なんにもない土地だったの。だから先人の知恵を借りて塩のないすんきを漬けて、あるものを生かし、自給自足で、生きていくしかなかったのよ」
と、御年90歳の佐口さん。10歳年下、80歳の森さんも思い出したように、
「そうよね、私たちの時代だって塩も貴重で、塩尻の塩屋にまで行って、はかりで測って買ってきたもん。」
と、続けます。

そこから話題は、かつてのお米づくりの苦労に。
「自動車もない時代は、お米を作っても中越(地区)から家まで背負って運んだんだもの、本当に苦労したの。私も、12歳になるころには、背板を背負って、米俵を担いでいたよ」(佐口さん)
じ、12歳には米俵を担いでいたなんて・・・! 一俵の重さは約60kg、どれほどの重労働だったでしょうか。
「油も貴重品。料理は煮物や、いろりで焼いたのが多くて、油なんてあんまり使わなかったね」
「川魚を釣るときは、飼っていたうさぎの肉を糀漬けにしたのを餌にしたね」
「豆腐も自分でつくった。ここいらでは、保存をよくするために、編んでおいた”こも”※で包んだ『こも豆腐』にしたんだよ」
※こも:稲わらで編んだむしろのこと
・・・と、次々語られるエピソードはまさに、「元祖ハードモードライフ」。
それでも、「なにもなかった時代」の苦労を語らうお二人の表情は、どこか楽しそうでもあります。
「木曽路はすべて山のなか。その奥の奥が、王滝よ」(佐口さん)
最後に手渡された『思い葉の抄』
うさぎやヤギを飼っていたときのことや、季節のごちそうのこと、全国から訪れる御嶽教の信者さんたちにお蕎麦を振る舞った日々のことなどなど、たくさんの思い出話をお聞きしたお茶飲みもそろそろ終わりの時間。
そんなとき、
「そうそう、これをどうぞ」
と佐口さん、おもむろに袋から冊子を取り出し、手渡してくれました。
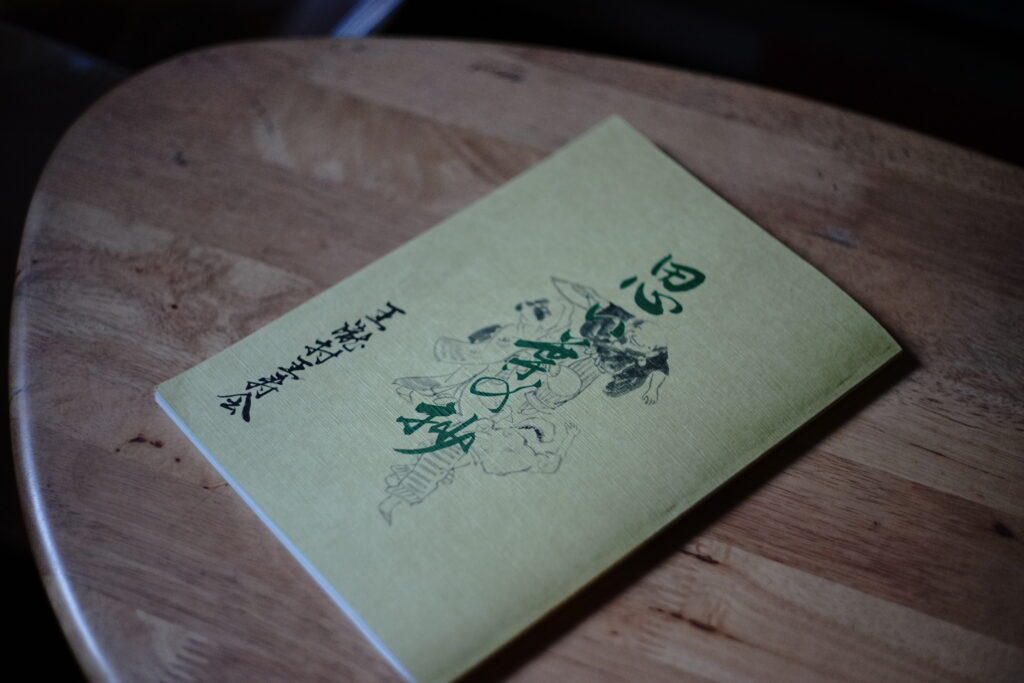
若葉色の表紙に書かれたタイトルは、『思い葉の抄』。
それは、村で歌い継がれてきたたくさんの民謡や方言、かつて地域で食べられていたものなどについて書き記された、貴重な記録集でした。
—
山や野の幸
・やまごぼう・山ぶどう・しゅうで ・いたどり ・うど・とち・わらび・ねいな(中略)・笹の実・笹の葉・から竿・・・・
川でとれたもの
・たなびら・いわな・かじか・(中略)・あじめ・たにし・がいら
山でとれたもの
・あとり・つぐみ・ひわ・山鳥・きじ・うそ・れんじゃく・・・
食用とした動物
・うさぎ_にわとり・熊・猪・山羊(大正末期)・乳牛(明治初期)・めんよう・いのぶた
・・・・
—
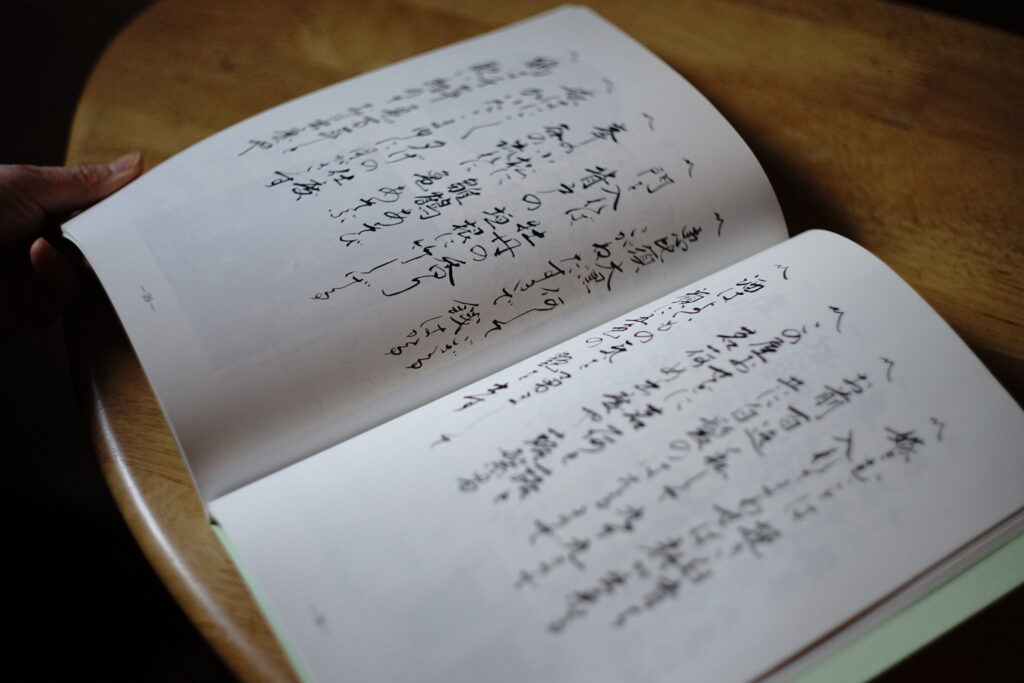
「王滝は、なんにもないなあ」
「いいところ?あるかしら」
佐口さんは飄々とした表情でそう言って笑いながらも、最後に手渡されたこの一冊のなかには、ご自身が大切にしたい、未来に伝えてほしい王滝の時間がまるごと詰まっているようでした。
すんきから始まった探訪の旅は、気づけばずいぶん王滝の奥深くにまでたどりついたのかもしれません。


 4°
4°