ここは「近藤太郎記念館」?
常八の壁にはぐるりと作品が
王滝村在住のアーティストであり、地域おこし協力隊の近藤太郎さんに話を伺ったのは、少しずつ春の訪れを感じはじめた2月終わりのこと。柔和な笑顔が印象的な近藤さんと、農家民宿&大衆酒Bar「常八」のテーブルを囲みました。
周囲を見ると、壁にも板戸にも、薪ストーブの背面にも、近藤さんの作品が描かれています。もはや「常八」の館内全体が、近藤さんの作品のようにさえ見えてくる、圧倒的な空間。これらの作品制作をきっかけに、神奈川出身の近藤さんは王滝を訪れ、そして村に暮らすこととなったのです。


東京の美術大学を卒業し、大学院まで修了した近藤さん。在学中、まずは「木曽ペインティングス※」への参加をきっかけに木曽エリアへと通うようになり、2年間、王滝村からほど近い木祖村での暮らしを経験しました。
※木曽ペインティングス:「宿場町と旅人とアートの至福な関係」を旗印に、江戸と京都の中間地点である木曽の宿場町を舞台に繰り広げるアートフプロジェクト
木祖村を拠点にアルバイトをしながらアート制作を行う日々のなか、常八オーナー・倉橋孝四郎さんの依頼でこの場所に絵を描くこととなり、これがご縁となって2022年には王滝村の地域おこし協力隊に就任。常八を暮らしの拠点に制作やアトリエづくりを行いながら、「上下流の関係人口創出」をミッションに協力隊としての活動を行う日々を送ってきました。
・
大学時代は、油彩画や写真、インスタレーションなど多様な手段を用いて「イメージ(作品の世界)と自分との関係性」をテーマに作品を制作。大学院在学中の2018年には、現代芸術家の登竜門の一つと言われる「シェル美術賞」でグランプリに輝く実力の持ち主ですが、「木曽に来たころは、2段階で悩んでいたんですよ」と、やわらかな笑顔のまま話してくれました。
「学生としての作品制作から、社会に出て絵を描くということへの変化、同時に関東の社会から木曽の社会に来た、という2段階の変化によって、『こういう場所でアートって、何の意味があるだろう?』という問いについても、もやもや考えてしまって」

「とくに『テーマ』というのが、自分にとってすごく難しくなってしまったんですよね」。
そう言ったあと、「でも」と続けた近藤さん。
「でも、王滝という場所でヒントをつかめたから、この村に移住したんだと思います」
王滝で開かれた、
「流域」というまなざし
悩めるアーティストが、王滝村でつかんだ「ヒント」。それは、村の歴史を語るうえで欠かすことのできない、「愛知用水プロジェクト」をめぐる物語のなかにあったのだとか。約60年前に実施されたわが国初の大規模総合開発事業とはいえ、今では知る人も少ないこのプロジェクト、一体、どのようなものだったのでしょう。
「愛知県の西部に位置する知多半島は長年、大きな河川がないことから水不足に悩まされる土地だったそうです。雨水をためて米作りをするような、慢性的に水が足りないその土地で、『このままではいけない』と立ち上がった人物の一人が、久野庄太郎さんでした。
久野さんは知多から遠く木曽を見て、『明治用水のように、木曽川から水を引けたら』と考えました。そして、ときに総理大臣へ陳情をしにいったり、浪曲師に明治用水にまつわる浪曲を書かせて市井の人々にこの事業の必要性とロマンを語ったり、自らの想いをさまざまな手法で人々に伝えていって、ついに王滝村から112キロメートルにわたる用水を通してしまったんです。すごい話ですよね」

よどみなく、まるでその場に立ち会っていたかのように生き生きと話す表情のなかに、近藤さんがいかにこの出来事を深く掘り下げ、関心を抱き、向き合ってきたのかがにじみます。
「今って、インフラの整備とかって『行政がいつのまにか整備してくれるもの』という感覚じゃないですか。でも、久野庄太郎さんはそうではなく、自分が必要なものを自分で歩いて計算し、『ここから引けばいい』と目標を定めて、仲間と一緒に行動していくんですよね。それって、自分たちは忘れかけているけれど、すごく地に足がついている行動だなあと、まず関心を引かれたんです」
久野正太郎さんの行動力と、それによってもたらされた物語に魅了された近藤さん。加えてもう一つ、新鮮な感動を覚えたことがありました。
「『流域』という世界の捉え方に、気付かされたんです。今、僕たちはつい、自治体ごとにエリアを捉えがちだけれど、山から海へと続いていくひと繋がりの範囲を考えるとき、一つの自治体には収まりきらない、『流域』という視座が不可欠です。
そのまなざしで見てみると、たとえば愛知用水の流域なら海辺の町から名古屋のような大都市につながり、周辺のベッドタウンから徐々に木曽の山へ入っていって……と、生活のリアリティは異なるのにつながっている暮らしが見えてくる。そういう、今の日常からは切り離されてしまった感覚について思いを巡らせることがすごく、好きでしたね」
さらに、王滝には、この事業に関わる忘れ得ぬ事実があります。それは、愛知用水実現のため、ダムの底に沈んだ集落があるということ。そのことも胸に置きながら、近藤さんは流域をつなぐ久野さんらの動きや、関わった人々の存在や記憶の断片のようなものをつなぎ合わせ、部屋をぐるりと取り囲む壁画へと記録するように描いていったのです。

そのためでしょうか、近藤さんの描いた壁画を眺めていると、たくさんの人たちの思い出に遠くから呼びかけられているような、記憶がこだまとなって聞こえてくるような、不思議な感覚に包まれます。
祭りのための日々ではない。
日常があってこそ祭りがある
こうして、画家としての壁画制作の仕事をきっかけに「流域」というテーマに行き当たった近藤さん。今度は「地域おこし協力隊」として、流域をテーマにした企画を立ち上げることを思い付きます。それが、協力隊就任から企画した「流域で繋がったらめでタイね」と「水記祭」というイベント。久野さんのように流域に足を運んだ体感を大切にしながら構想を描き、県内外のアーティストや住民を巻き込んだイベントは大きな話題を呼び、折しも愛知用水事業60周年の節目に事業の記憶を未来につなぐ新たな1ページとなりました。



(写真=山口直人)

(写真=山口直人)
ところが近藤さん、
「いやあ、でも、これは2年やって、疲れちゃって」
と、照れたように苦笑。
「やっぱり、112キロ道のりって遠いんですよね。車だと4時間ぐらいの距離。これをあちこち駆け回りながら一つのイベントにまとめあげるのは本当に大変でした。
続けられないよなあ、と思っていたところ、ちょうど昨日、かつてネイティブアメリカンと生活をしていたという人に、『ネイティブアメリカンの種族のなかには、一年のうちに4日間、飲まず食わずの祭りを行う』って聞いたんですね。でも、彼らはこう捉えているそうです。『祭りの4日間が大事なのではない、他の日常が大切だから祭りをするんだ』って。それを聞いてより一層、『これからは祭りの1日のために費やす日々じゃなく、普段の日々をどうつくるか、というほうにフォーカスしていったほうがいいな』って思ったんです」

イラストは、かつて木曽で地域おこし協力隊をしていた北原千絵さんによるもの
未来は思い出せないから。
過去とのつながりのなか、今を重ねて
作品づくりに祭り企画実行にと、激動の(?)王滝村ライフを2年間すごしてきた近藤さん。今年4月にはついに「常八」での暮らしを卒業し、村内に古民家を借りて暮らし始めました。しかしじつは、常八の壁画にまだ一部、未完成な部分があるのだそう。たしかに、淡い色彩が施された壁面のなかに、まだ鉛筆の線のみが走っている部分がありました。
「この壁画は、愛知用水の歴史を絵巻物のように描いているんですが、最後に『未来』の部分を描いてほしいというのが孝四郎さんからの依頼で、でもまだ描けなくて」と、近藤さん。
「この辺りなんて、描き始めたのは一昨年ぐらいなんですけどね」と、改めて白い壁に向き合います。

完成するのは、いつの日か……。じっと絵を見つめたまま、こんな話を続けます。
「でも、なんとなく『過去は大切かな』というイメージはあるんです。なぜなら未来って、”思い出す”ことはできないじゃないですか。自分自身も、この先どうなっていくかわからない。でも過去と、今の日々の暮らしのなかから、何かを描いていける気がしています」
未来は思い出すことができない。だからこそ、過去と今、ここにある日々を大切に。王滝での暮らしのなかでたぐり寄せたそんな思いは、はからずも倉橋さん運営の合同会社Rext滝越の理念にもつながっているのだとか。
「もともと、自分でなにかを決めるのは得意じゃない。都会にいても村にいても、『ここでいいのかな』と落ち着かない部分は常に残る気がする。ただ、強い思いを受け取ると、こちらにも強い思いが湧いてきます。(倉橋)孝四郎さんはまさに、強い思いとともに僕に絵を依頼してくれた。それがすでに、僕が今、王滝に暮らし、作品をつくる意味なのかもしれません」
移住というと、仕事はどうする、住まいは?と考えてしまいがち。けれど王滝村には想像よりもずっと多様な移住の道のりと暮らしがあることを、近藤さんは示してくれていました。この先も、時間をかけてゆっくりと、未来の絵を描いていくのでしょう。


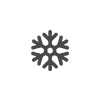 1°
1°